|
*大牟田市に水道のないころ
大正7年ごろ、大牟田市は人口がふえ、湿地や沼地などもうめたてて家をたてました。ところが、このようなところは土地がひくく、水はけが悪いので下水が井戸の中へしみこんで水がのめませんでした。下のグラフからもわかるように、ほとんどの井戸水がのめませんでした。とくに、大牟田川ふきんの井戸水は黄色っぽく、その上くさくなっていました。
このように、きれいな水が不足していたので、しかたなく体に悪い水を使っていました。そのため腸チフスなどの伝せん病が毎年はやって、人々はこまっていました。また、炭こうのさい害で水が出なくなった井戸もありました。
*大正7年は
1918年
|
*湿地や沼地
川やみずうみのちかくで、
じめじめした土地
|
*腸チフス
腸チフス菌が食べ物といっしょに体内に入って、
腸がおかされる病気。高い熱が出て、げりをする。
|
                  
|
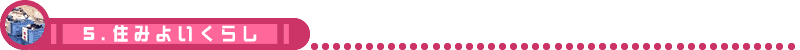
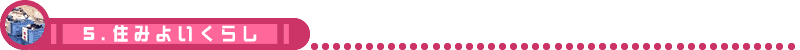
![]()