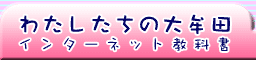
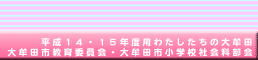
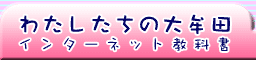 |
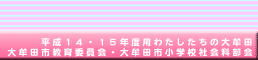 |
|
|
◆ 年 表 ◆
|
|
大牟田のうつりかわり |
||||
|
|
おもなできごと |
人口の うつりかわり |
町やくらしの ようす |
|
|
む か し の こ ろ |
文明元年 (1469) |
○とうか村のでんじざえ門が石炭を発見した。 |  |
|
| 天正十五年 (1587) |
○たかはしなおつぐが三池郡一万八千石をたまをり、三池地方の領主となる。 | |||
| 慶長五年 (1600) |
○たかはしなおつぐが領地を取り上げられ、田中吉政が筑後の国の領主となる。 | |||
| 元和七年 (1621) |
○立花種次が三池藩一万石をたまわり、三池藩主となる。 | |||
| 延宝二年 (1674) |
○早鐘池の水を通すために眼鏡橋をつくり、その上に水路をもおけて、片平・大牟田方面の水田をうるおす。 | |||
| 文化三年 (1806) |
○三池藩は奥州下手渡(今の福井県月舘町)に移され、 三池郡十五ヶ村は天領地となった。 ○稲荷山の石炭は、藤本伝吾がほるようになった。 |
|||
| 嘉永三年 (1843) |
○三池の五ケ村が三池藩にもどされた。 | |||
|
明 治 の こ ろ |
明治六年 (1873) |
○三池炭こうが国のものになった。 |
四千人 | 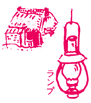 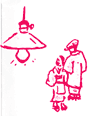  |
| 明治九年 (1876) |
○浜田又平が小浜開七〇町あまりの干拓をはじめた。 | |||
| 明治十一年 (1878) |
○大浦港から石炭を運びだすため、大牟田川河口まで馬車鉄道が通った。 | |||
| 明治二十二年 (1889) |
○三池炭坑が「三井」のものとなった。 ○いくつかの村がいっしょになり、大牟田町、三川村、駛馬村、三池町、手鎌村、銀水村、倉永村、上内村、玉川村となった。 |
大牟田町 一万一千人 |
||
| 明治二十四年 (1891) |
○大牟田に汽車が通るようになり、国鉄(今のJR)大牟田駅ができた。 | |||
| 明治二十七年 (1894) |
○七浦に火力発電所ができて、抗外にに電とうがつくようになった。 | |||
| 明治三十四年 (1901) |
○大牟田で初めて自転車が売りはじめられた。 | |||
| 明治三十五年 (1902) |
○大牟田港(ちっ港)ができた。 | 二万四千人 | ||
| 明治三十六年 (1903) |
○大牟田ゆう便局に電話がとりつけられた。 | |||
| 明治四十一年 (1908) |
○三池港ができてイギリス船ペーナポン号が入港してきた。 | |||
|
大 正 の こ ろ |
大正元年 (1912) |
○三川村の人口がふえ、三川町となった。 |
四万一千人 |  |
| 大正三年 (1914) |
○三池せいれん所がうんてんを開始した。 | |||
| 大正六年 (1917) |
○大牟田町の人口がふえ、大牟田市となった。 | 大牟田市 六万八千人 |
||
| 大正十年 (1921) |
○大牟田にはじめて水道ができた。 | |||
| 大正十五年 (1926) |
○国鉄(今のJR)の銀水駅ができた。 | |||
|
昭 和 に な っ て |
昭和二年 (1927) |
○市内電車が通い始めた。(旭町ー四山) ○バスも通い始めた。(大牟田駅ー三池町) |
十万二千五百人 |  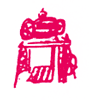    |
| 昭和四年 (1929) |
○三川町が大牟田市といっしょになった。 | |||
| 昭和六年 (1931) |
○港発電所がうんてんを開始した。 | |||
| 昭和八年 (1933) |
○市役所が火事でやけた。 | |||
| 昭和九年 (1934) |
○五月より八月にかけて腸チフスがはやり、五百八十人あまりの病人が出た。(死者九十七名) | |||
| 昭和十一年 (1936) |
○今の市役所ができあがった。 | |||
| 昭和十二年 (1937) |
○ばくはつセキリで病人一万二千人、死者七百十二人がでた。 | 十七万九千人 | ||
| 昭和十三年 (1938) |
○西鉄電車が大牟田までかよいはじめた。 | |||
| 昭和十五年 (1940) |
○三川抗で石炭をほるようになった。 | |||
| 昭和十六年 (1941) |
○玉川村、銀水村、駛馬町、三池町が大牟田市といっしょになった。 | |||
| 昭和十七年 (1942) |
○小浜のていぼうがこわれ、大牟田はじまっていらいの大水害にみまわれた。 | |||
| 昭和二十年 (1945) |
○空襲で大牟田のほとんどの家がやけた。 | |||
| 昭和二十四年 (1949) |
○市の保健所ができた。 ○大牟田市立病院ができた。(昭和二十五年) |
十九万九千人 | ||
| 昭和二十七年 (1952) |
○市内電車がはいしされ、バスが多くなった。 | |||
| 昭和二十八年 (1953) |
○人工島(初島)ができた。 | |||
| 昭和二十九年 (1954) |
○もとの市民会かんができた。 | |||
| 昭和三十二年 (1957) |
○大牟田市で産業はくらん会があった。(市になって四十年記念) | |||
| 昭和三十五年 (1960) |
○三池炭坑のそうぎが十ヶ月つづいた。 | |||
| 昭和三十八年 (1963) |
○三川抗で炭じんばくはつ事故がおこり、死者四百五十八名を出した。 | |||
| 昭和四十二年 (1967) |
○三池かんたくができ上がった。 ○大牟田川や空のよごれが問題になった。 |
十六万六千人 | ||
| 昭和四十三年 (1968) |
○えんめい配水池ができた。 | |||
| 昭和四十五年 (1970) |
○西鉄新栄町が現在地に移転し、商店街ができた。 ○三井アルミで仕事がはじまった。 |
|||
| 昭和五十年 (1975) |
○きくち川からも水道の水をひくようになった。 | |||
| 昭和六十一年 (1986) |
○大牟田文化会館ができた。 ○筑後川からも水道をひきはじめ、甘木配水池がつくられた。 |
|||
|
平 成 に な っ て |
平成二年 (1980) |
○とびうめ国体(ソフトボール・ボクシング)がひらかれた。 | 十四万八千人 | |
| 平成三年 (1991) |
○カルタックスおおむたがオープンした。 ○JR吉野駅ができた。 |
|||
| 平成四年 (1992) |
○延命動物園が新しくなった。 | |||
| 平成六年 (1994) |
○すわ公園ができた。 ○大牟田市内に七つの地区公民館が全部できあがった。 |
|||
| 平成七年 (1995) |
○ネイブルランド・石炭産業科学館がオープンした。 ○市立総合病院ができた。 |
|||
| 平成九年 (1997) |
○三池炭坑が閉山した。 | |||
| 平成十四年 (2002) |
○RDFセンターができる。 | |||
| 平成十五年 (2003) |
○勝立配水地ができた。 | 十三万七千人 | ||
![]()